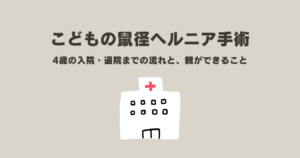3歳の娘が一週間以上の入院をしました。
前記事では、付き添い入院の持ち物リストについてまとめました。
お子さんの付き添い入院。
不安な気持ちのなかで「どんな風に過ごすんだろう?」と、想像がつかずに戸惑ってしまうこともありますよね。
この記事では、3歳11ヶ月の娘との9日間の付き添い入院を経験した私の体験をもとに、入院中のママの1日の過ごし方をご紹介します。
病院の設備や方針によっても異なる点はありますが、「こんな風に過ごせるんだ」と少しでも参考になれば嬉しいです。
病室の選び方と実際の環境

入院前に、個室か総室か選ぶことができました。
案内されたお部屋は2人用の部屋でしたが、幸運にも同室に他の患者さんがおらず、ほぼ個室のような環境で過ごすことができました。
個室と総室、それぞれの特徴は以下のとおりです。
個室
- 1人部屋。有料。
- お部屋によってトイレやシャワーが設置されている。
- 部屋の中で通話ができる。
- 周囲に気を遣わなくていいので、気持ちが楽。
総室
- 2〜4人部屋。室料なし。
- トイレやシャワーは部屋の外にある。
- 通話する場合はロビーへ移動する。
- 物音など、周囲に気を遣う。
付き添いママの食事は申請可能?コンビニ?

娘の食事は病院食が用意されていますが、付き添いの私の分は自分で用意する必要がありました。
食事を自分で調達する場合、病院内の別フロアにあるコンビニまで買いに行きます。
一方で病院によっては家族用の病院食を有料で申請できる場合もあります。
今回の病院では、1食あたり約650円でお願いでき、3食すべて申請しました。
病院食を申請した場合
- 温かいごはんを病室まで届けてもらえる
- 食事の準備や買い出しの手間が省ける
- 「今日は何食べよう?」と考えずに済む
個人的には、食事のたびに温かく栄養バランスのとれた食事が届くことが、とてもありがたく感じました。
なにより、「食べるものを考える」「買いに行く」という小さな負担が消えることで、娘のお世話により集中できたのは大きかったです。
(追記)
ちなみに翌年、別の病院で1泊2日の付き添い入院をした際は、家族用食事の提供自体がなく、すべてコンビニで調達しました。1泊2日と短い入院でしたが、結構しんどいなぁと個人的に感じました。
コンビニを利用した場合
- 食べたいものを自分で選べる
- 買いに行く手間がかかる
- 毎回「何を食べよう?」と決断疲れする
入院前に、付き添い家族の食事についても病院側に確認しておくと安心です。
もし自分で食事を用意する必要がある場合は、コンビニを利用するだけでなく、小腹がすいたとき用に常温保存ができる軽食を持参しておくのもおすすめです。移動できないタイミングや、夜中に小腹がすいたときにも助かりますよ。
翌年の付き添い入院時、コンビニで調達しましたが、手軽に食べられて美味しかったです。
入院中のお風呂は?子どもと一緒にシャワー

入院中のお風呂について。私たちが入院した病院では病棟内にシャワールームがあり、子どもと一緒に入ることができました。娘はまだ3歳だったので、ひとりでシャワーを浴びるのは難しく、毎回ふたりで一緒に入っていました。
看護師さんが予約してくださった時間に、シャワー室を利用する流れです。
使用時間は30分と決まっていたため、時間厳守するためにスマホのアラームを活用していました。
体を洗って、子どもと自分の着替えを済ませて……と、30分は意外とあっという間。
もう少し余裕があれば…と思う日もありましたが、毎回なんとか時間内で済ませていました。
シャワーのあとは、落ちた髪の毛などをさっと拾っておくと、次に使う方も気持ちよく使えます。
睡眠時はどんな感じ?添い寝と、ママの体力管理

入院中の夜は、こどもが使っているベッドで一緒に添い寝していました。
3歳の娘と並んで寝るには少し狭く、寝返りを打つのも難しい状態でしたが、娘にとっては「ママと一緒」という安心感があったようです。
病院によっては、付き添い者用のベッドを貸し出してもらえるところもあります。
夜間の病棟は、電子音が響いたり、看護師さんの巡回で何度か部屋の扉が開いたりと、いつもとは違う環境。
そんな中でも、娘は思いのほかよく眠ってくれました。
ただ、私はというと、日によって眠れなかったり、夜中に何度も目が覚めたり…。
体力的にきつい日もありました。
そんなときは、無理をしすぎず、娘と一緒にお昼寝をしたり、自分の体を労わる時間も意識して取り入れるようにしていました。長期の付き添い入院では、ママの体力やメンタルの管理もとても大切です。
眠れないときは、耳で聴けるAudibleが気分転換になります。

「ママがいない!」を防ぐために

就寝中にトイレへ行くとき、子どもがふと目を覚まして「ママがいない!」と不安になってしまうこともあるかもしれません。
病院によってはトイレが病室の外にあることも多く、ほんの数分でもママが席を外す場面は意外とあるものです。
そんなときに備えて、何度か娘にこう声をかけていました。
「夜、ママがトイレに行くことがあるけど、すぐ戻ってくるから大丈夫だよ」
「ママが見えなくても、ちょっとだけだから安心しててね」
子どもが小さくてもやさしい言葉で事前に伝えておくと、驚かず落ち着いて過ごせるように思います。
通信環境は?Wi-Fiとテレビ電話の活用について

私たちが入院していた病院には、フリーWi-Fiが用意されていました。
病棟内は携帯の電波が弱くなることもあったので、Wi-Fiが使えるのは本当にありがたかったです。
とくに助けられたのが、家族とのテレビ電話。
コロナの影響で面会がほとんどできなかったので、家族と画面越しに顔を見て話せる時間は、娘にとっても私にとっても励みになっていました。
電波が不安定だと、音声が途切れたり映像が止まったりして、かえってストレスを感じることもありますよね。
その点、Wi-Fiのおかげで安心して連絡をとることができたのは、本当に助かりました。
ただ、利用するたびにメールアドレスを入力し、届いたURLで認証する必要があり、最初は少し戸惑いました。
事前に接続方法を確認しておくと、スムーズに使えると思います。
小児病棟のプレイルーム

小児病棟には、子どもたちが遊べる「プレイルーム」がありました。
私たちが入院した病院では、平日の日中に保育士さんが常駐されていて、付き添い中の親にとってもとても心強い存在でした。
たとえば、私が病院内のコンビニに行きたいときなど、娘を少しのあいだ見ていただけるのは本当に助かりました。
プレイルームにはおもちゃがたくさん用意されていて、娘はすっかり気に入っていました。
「今日もプレイルーム行きたい!」と毎日のように楽しみにしていて、保育士さんとお話したり、一緒に遊んでもらったりする時間が良い気分転換になっていたようです。
入院中も「遊びの時間」があることで、子どもなりに安心できたり、気持ちがほぐれたりするんだなぁと、私自身も実感しました。
(追記)
翌年、別の病院で付き添い入院をした際にもプレイルームや保育士さんの存在はありましたが、病院によって関わり方はさまざまだと感じました。
おもちゃの貸し出しはあっても、遊んでもらえる時間はほとんどありませんでした。病院ごとにルールや運営スタイルは違うようです。
それでも、プレイルームは子どもにとって良い息抜きになります。
お部屋とはちょっと違う空間で遊ぶだけでも、気分が変わりますし、親子ともに助けられる場面がきっとあると思います。もし病棟にプレイルームがあれば、ぜひ活用してあげてほしいと思います。
おわりに:付き添い入院を頑張るママへ

以上、入院中の過ごし方についてまとめました。
初めての付き添い入院は、不安も戸惑いもたくさんあると思います。
しかし、お子さんが「ママが一緒だから安心」と感じられることが、何よりのケアです。
この記事が、これから付き添い入院をされる方の参考になれば嬉しく思います。
どうか、お子さんとママにとって、少しでも穏やかな入院生活になりますように。
一週間の付き添い入院の持ち物リスト

翌年に入院・手術に付き添いしました。