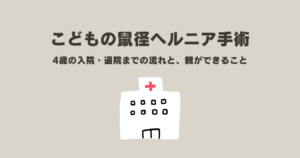先日、3歳娘の持病が悪化してしまい、1週間以上の入院を経験しました。
急なことだったため、付き添う私自身もバタバタと準備を進めることに……。
慌てて荷造りした中で「持ってきてよかった」と感じたもの、「なくても大丈夫だったな」と思ったものがありました。今回はその実体験をもとに、3歳児の付き添い入院で役立った持ち物リストをご紹介します。
「子どもの入院が決まったけれど、何を準備すればいいかわからない」
「付き添い生活を少しでも快適に過ごしたい」
そんな方のお役に立てたら嬉しいです。

付き添い入院の持ち物リスト

1週間の入院のために、実際に使用した持ち物をリストにまとめました。
| カテゴリ | 持ち物 | コメント |
|---|---|---|
| 必要なもの | 診察券 | 受診に必要なもの |
| 健康保険証 医療証 | ||
| お薬 お薬手帳 | 普段 飲んでいるお薬。 | |
| 必要な書類 | 誓約書などの書類を事前に記入しておく。 | |
| 母子手帳 | 小児科受診のため。 | |
| こども衣類 | 洋服 | 1日分。入院中は寝衣で過ごすので、退院時の服装があればOK。 |
| (寝衣)※ | レンタルできる場合は不要。 持参する場合は多めに。 | |
| 下着 | 多めに準備する。 | |
| 靴下 | 多めに準備する。 | |
| おとな衣類 | 病院内で過ごす服(複数) | コンビニに行けるくらいの服装。 |
| 寝るときの服(複数) | リラックスできる服装。 | |
| 下着 | 多めに準備する。 | |
| 靴下 | 多めに準備する。 | |
| こども生活用品 | おむつ | 就寝時のみ使用しました。 予定の入院日数より多めに準備。 |
| 歯ブラシ 歯磨き粉 コップ | 普段使っている洗面道具。 | |
| スリッパ | 脱ぎ履きしやすい室内履き。 (病院によってはスリッパNGの場合も) | |
| こども用マスク | 病棟内を移動するときなどに着用。病院内のコンビニで買い足しました。 | |
| トレーニング箸 | まだお箸が使えないので、普段使っているトレーニング箸を夫に届けてもらいました。 | |
| おとな生活用品 | 歯ブラシ 歯磨き粉 コップ | 普段使っている洗面道具。 |
| コンタクトレンズ 洗浄液 眼鏡 | 視力の良い人は不要。 | |
| 洗顔フォーム 化粧水 乳液 | 小さなボトルに詰め替えておくと荷物軽減に。 | |
| アイメイク類 アイブロウ リムーバー 保湿リップ | ノーメイクで問題ありませんが、自分が落ち込まない程度に整えました。 マスクで過ごすので、ベースメイクは省略。 | |
| おりものシート (生理用品) | 生理予定日が近い場合は、生理用品の準備を。 | |
| お薬 | 飲んでいるものがあれば。 | |
| スリッパ | 脱ぎ履きしやすい室内履き。 (病院によってはスリッパNGの場合も) | |
| マスク | 予定の入院日数より多めに準備。 | |
| 生活用品 | (タオル)※ | レンタルできる場合は不要。 持参する場合は多めに。 |
| シャンプー コンディショナー ボディソープ | 親子で使えるもの。 トラベル用はコンビニでも購入できました。 | |
| ベビー綿棒 | 耳掃除やメイク落としに使うことがあれば。 | |
| ティッシュ(箱) | 1週間で2箱使用しました。 | |
| ウェットティッシュ | 食事中にこどもの口元やテーブルを拭いたり、よく使いました。おしりふきで代用可能。 | |
| 100円玉 (多め) | コインランドリーの使用に、100円玉がたくさん必要でした。 1回の利用目安:洗濯~乾燥500円、追加乾燥100円 | |
| ガジェット | iPhone | 連絡以外にも、シャワー時のタイマーに使用しました。 |
| イヤホン | AirPods。ビデオ通話するときに使用。 | |
| タブレット | ネットを繋がなくても遊べるアプリを事前にダウンロードしました。 | |
| Apple Watch | 振動アラームが設定できるので、目覚ましや薬のリマインドに活用しました。 | |
| 各種 充電器 | iPhoneとApple Watchは毎日充電。 | |
| 延長コード | コンセントが壁の高い位置にあったので、延長コードがあると便利でした。 | |
| スマホ用スタンド | ビデオ通話をするときに使用しました。 ※無くても問題ありません。 | |
| その他 | 財布 | コンパクトな財布。ポシェットに入れて持ち歩きました。 |
| 自宅の鍵 | 帰るときに必要。 | |
| ボールペン | 薬やスケジュールについてメモを取るときに使いました。 | |
| 紙やノート | 入院中に勉強会があったのでメモをとりました。娘のお絵描きにも。 | |
| ビニール袋 | 使った衣類をまとめたり、ゴミを入れたり。数枚あると安心。 | |
| トランプ | こどもの気分転換に。 | |
| おりがみ | こどもの気分転換に。 |
ポイント
- 荷物はキャリーケースにまとめました。
病院によってはNGのこともあるので、事前の確認を忘れずに。 - 貴重品は小さなポシェットに入れて、常に身につけていました。
付き添いママが少しでも楽になる、準備のコツ
小さな子どもとの入院生活は、思っている以上に体力も気力も必要になりますよね。
私が実際にやってよかったことを3つご紹介します。
病院でレンタルできるものは活用する

わたしが入院した病院では、下記のものが有料でレンタル可能でした。
- タオル類
- 小児用 寝衣
- 大人用 寝衣
- おむつ
今回は約1週間の入院ということで、わが家はタオル類と小児用の寝衣をレンタルすることに。
どちらも毎日使うものなので、洗濯の手間がなくなるのは本当に助かりました。
レンタル品の有無は病院によって異なるので、入院前に確認しておくと安心です。
「全部持っていかなくちゃ!」と気負わずに済むだけで、かなり気持ちがラクになりました。
家族向けの食事サービスは利用できると助かる

病院によっては、付き添いの家族向けに食事を提供してくれるサービスがあります。
わたしが利用した病院では、朝・昼・夕の3食を希望制で申請でき、1食あたり約650円ほどでした。
病院内にはコンビニもありましたが、入院中は子どものお世話に気を取られて、自分の食事のことまで気が回らないことも…。毎食どうしようかと考えたり、買いに行くタイミングを見つけたりするのが意外と負担になりがちです。
その点、事前に食事をお願いしておけると、「今日は何を食べよう…」と悩む時間が減り、子どもに集中できたことがとても助かりました。
ちなみに翌年、娘が手術で入院した際、その病院には家族用の食事提供サービス自体がありませんでした。
そのときは病院のコンビニで毎食を調達しましたが、たった1泊2日でも「結構しんどいな…」と実感。
もし付き添い用の食事を用意してもらえる病院であれば、積極的に利用するのがおすすめです。
少し費用はかかりますが、心身の負担が減ることと、精神的にも安心感が違います。
リスト化しておくと安心。抜け漏れ防止にも

入院の準備は、急なことも多く、気持ちがバタバタしてしまいがち。そんなときこそ、必要な連絡や書類、持ち物をリスト化しておくことで、心に少し余裕がうまれます。
わが家では、付き添い入院が決まった前日に、以下のような準備をしました。
職場や保育園、習い事への連絡
入院が決まったら、まずは職場と保育園へ連絡を入れました。
お子さんが習い事をしている場合は、そちらにも忘れずお休みのご連絡を入れておくと安心です。
連絡は先に済ませておくと気がかりがひとつ減ります。
病院から渡された書類の記入
入院の案内と一緒に渡される、いくつかの大切な書類。
入院同意書や各種申請用紙などは、あらかじめ記入を済ませておくと、当日の手続きがぐっとスムーズになります。
特に気をつけたいのが、「連帯保証人」の欄など、自分以外の人に記入してもらう必要がある部分。
どなたにお願いするか、いつ記入してもらうかなどを早めに確認しておくと安心です。
 デイジー
デイジー病院からの書類は、受け取ったら即確認!
持ち物リストを書き出す
荷物の準備も、頭の中だけで考えていると「何か忘れてる気がする…」とモヤモヤしがち。
私はスマホのメモアプリに、入院に必要そうなものをカテゴリごとにリスト化しました。
「子ども用」「自分用」などに分けておくと見やすく、準備中にもチェックしやすいんです。
また、このリストは退院時にも活躍!
帰るときに「持ってきたもの、ちゃんと全部あるかな?」と見直すことで、忘れ物も防げました。
ママの心もケアしよう。付き添い生活中のメンタル対策

慣れない環境での寝泊まり、子どもの看病…。
付き添いママにとっては、体だけでなく心にも負担がかかります。
だからこそ、自分の心をいたわる時間もほんの少しでも持てるといいなと思いました。
入院中に、読書はできる?
「付き添い中は、空いた時間に本を読んだり…」と想像していたのですが、現実はちょっと違いました。
病院では一日中子どものお世話をするため、予想以上にまとまった時間はとれません。
本も持参していたのですが、読む余裕はほとんどありませんでした。
(しかも、消灯時間になると部屋が暗くなるため、紙の本は読みづらいです。)
とはいえ、気分転換の手段をいくつか用意しておくのはおすすめ。
期待しすぎず、あくまで“お守り”のような存在にしておくと、気持ちもラクになります。
AudibleやKindleで『ながら読書』を味方に
まとまって読書する時間はなくても、耳で聴けるオーディオブック(Audible)や、スマホで気軽に読めるKindleがあると少し気分転換になりました。
慣れない環境でなかなか寝つけない夜は、ベッドの横で横になりながら、子どもが寝たあとにイヤホンで音声を聴くだけでも、心がほぐれると思います。
耳で聴けるAudibleの活用法

がんばりすぎないで、ママ自身のケアも

初めての付き添い入院は、わからないことばかりで戸惑いや不安も大きいかもしれません。
さらに、長期の入院生活となると、どうしても心が疲れてしまう瞬間もあると思います。
無理をせず、ご自身のケアも大切にしてくださいね。
娘の付き添い入院をした体験をもとにした入院関連記事をいくつかご紹介しています。
付き添い入院の過ごし方について

翌年、娘が手術を受けたときの入院準備から退院まで